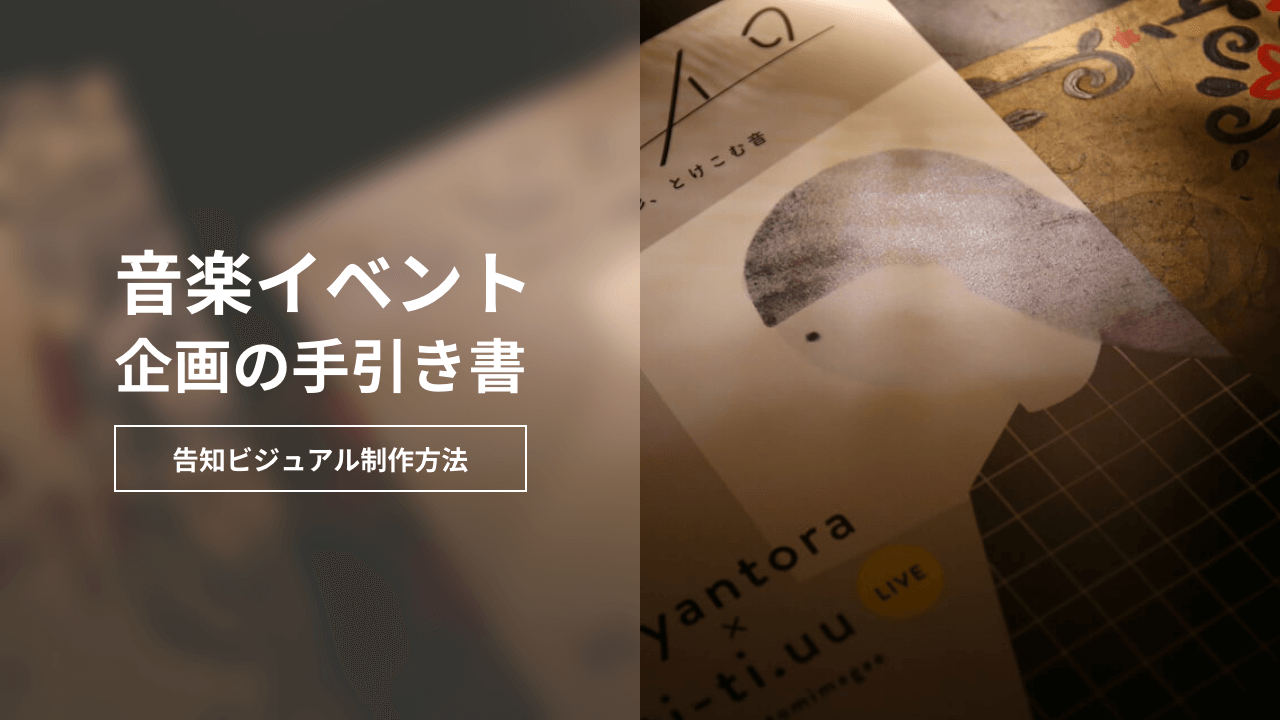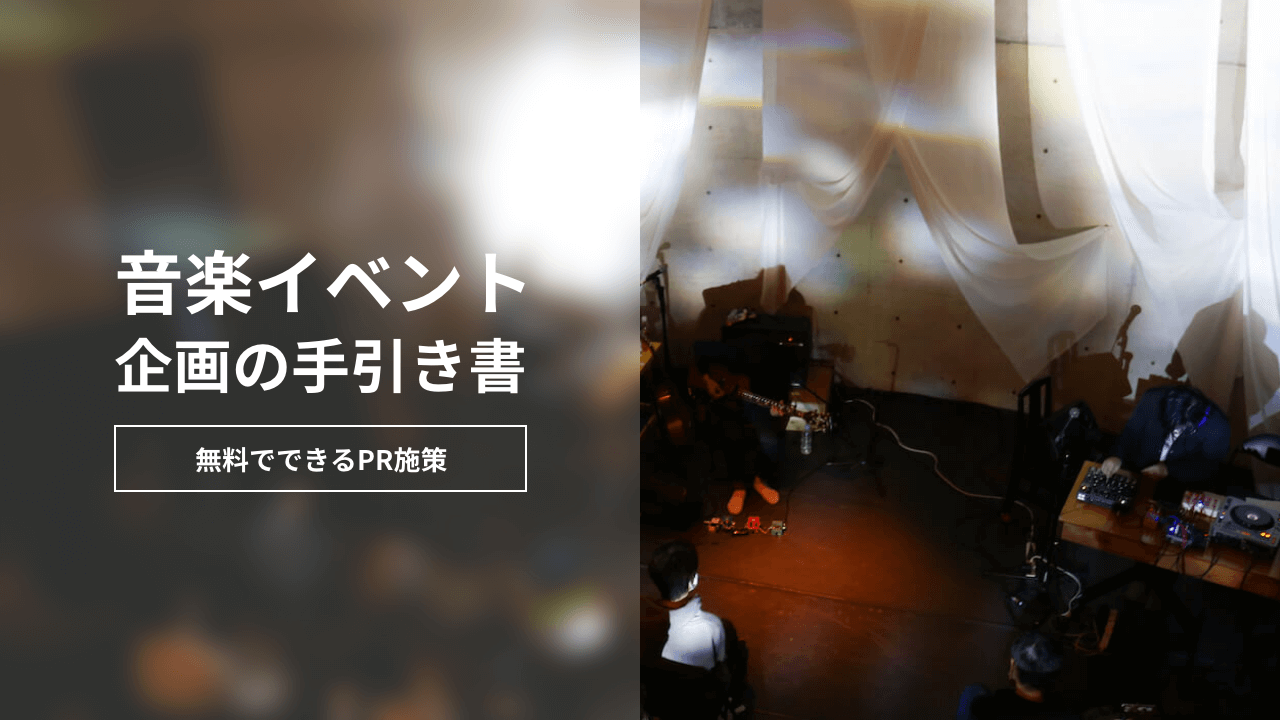この記事は、音楽イベントを自分で開催したい!と思っている方へ向けて、大まかな流れの紹介と、より魅力的なイベントを実現するためのポイントについて書いた連載記事です。
新型コロナウイルスの感染拡大により、音楽イベントの数は減ってしまいました。それでも、音楽は心に光を届けてくれるもの。
プラネタリウムやゲストハウスなどで、最大150名規模の音楽イベント企画を開催してきた立場から、今後も小さくてもあたたかい音楽の場・文化の灯が続いていくことを願って、イベントづくりで経験してきたことを記事にまとめて発信することにしました。
全部で9記事あり、今見ている記事は3記事目です。各記事に書いている内容や、どんな人が書いているかは1記事目に書いています。
各所へのオファー
どんな音楽イベントにしたいか企画の整理ができたら、次はオファーです。イベントを開催する会場、出演してくださるアーティスト、運営を共にお願いするスタッフなど、関係者にオファーしていきましょう。
前記事のように「企画書」を用意しておくと、情報共有がスムーズです。
事務的な連絡ではなく、あなたにお願いしたい!という熱量ある文章をしたため、失礼のないように丁寧な言葉でメッセージを送りましょう。このとき重要なのは、依頼関係に留まらない、共にイベントを形作る仲間のような存在としてお願いすることです。
コンセプトの記事では、企画者が企画を深く考えていくことの大事さを書きました。しかし、イベントは複数の人間の感情で動く生き物のようなもの。そして音楽も心に訴えかけるものです。
会場、出演者、スタッフなどイベントを共に形作る人たちが、大元の企画に共感し、それぞれの視点でどんどんアイディアを広げてくれることで、一人では実現できなかったような素晴らしい瞬間が生まれるのも、イベントの醍醐味のひとつ。
そのためにも、最初のオファー時の姿勢が重要になります。
会場へ相談する
イベント開催にあたり、まずは開催場所との調整が必須です。外部イベンターによる企画イベントの開催が可能かや、開催日時、料金や機材など諸々すり合わせていきましょう。
この時、オファー前に実際に現地に訪れることをおすすめします。写真や動画を撮り、広さや雰囲気などをお客さん目線で確かめていきましょう。
この会場がいい!と思った時は、会場の方に「すみません、音楽イベントの開催って可能ですか..?」と伺うという手もあります。うまくいけば、担当者にお繋ぎいただき、具体的な相談ができることもあります。くれぐれも失礼のないようにお伺いしましょう。
オファー時に重要な要素として「なぜその会場でないといけないのか?」をはっきり伝えましょう。アクセスやキャパなどだけでなく、その会場ならではの世界観やストーリーに紐づく理由だと相手も喜んでくれるはずです。

晴れて利用承諾を頂ければ、具体的な相談も兼ねて、一度お打ち合わせをお願いしましょう。慣れてくれば図面や機材リストを回収し、あとは本番だけ・・という流れでも開催自体はできますが、重要なのは、会場担当者もイベントを共に成功させる仲間として関わっていただくことです。
会場を歩きながら、ステージの位置やお客さんの導線を話したり、控室や受付など場所の確認をしたり、会場にお借りできる機材の確認をしましょう。あとで関係者に共有しやすいように、写真は多めに撮っておくことがおすすめです。
実現したいイベント内容を熱量持って話し、会場をどう活用したいかを伝えるうちに、会場担当者も自然と企画に共感したり、あなた自身を応援したい、そしてイベントを一緒に成功させたい!と思ってくれるでしょう。そして、会場担当者からも、ここはこうした方がおもしろいかも!というアイディアが出てくると、イベントはどんどん魅力的になっていきます。
例えば『タビノエ』を開催した会場は、蔵前のゲストハウスNui. HOSTEL & BAR LOUNGE。通常は宿泊施設であり、ライブイベントは日常的には行っていません。しかし企画に共感いただき、あれこれ話す中で「Nui.としても旅や風景を感じさせるオリジナルカクテルを準備できる」と仰っていただき、イベント限定ドリンクが生まれました。

イベント体験において重要な会場へは、相談事項が盛りだくさん。会場にとっても楽しいイベントパートナーとして受け取ってもらえるように、しっかり信頼関係を築いていくことが大切です。
出演者へオファーする
会場と日時が決まったら、次は出演者です。好きなアーティストに想いを込めてオファーしましょう!
アーティスト側は普段の音楽活動でお忙しいことが多いです。そのため概要は簡潔に、「なぜオファーしたいのか」は熱烈に送りましょう。謝礼金額も最初のメッセージに明記しましょう。
私はホームページのCONTACTから送ることが多いですが、見つけられない場合はSNSのDMという手もあります。アーティストによってはマネージャー宛にメールが届くこともあるでしょう。とにかく丁寧なメールを心がけましょう。
アーティスト活動のタイミングや条件面など様々な理由で断られることも多いですが、企画意図に共感いただけると意外とOKしてもらえます。初めは繋がりのアーティストからお願いし始めるとスムーズですが、徐々に実績を作ることで繋がりのないアーティストにもOK頂きやすくなるでしょう。
アーティストと繋がりがない時は、ライブへ遊びに行き、物販など話せるタイミングで「個人企画のイベントにお誘いしたいと思ってます! メールお送りしてもよいですか?」とお伝えすることで、きっかけを作ることもできます。まずは勇気を出してやってみましょう。

出演にOKいただけたら、告知に利用させていただくプロフィール素材と、本番の機材セット図を頂くよう依頼しましょう。機材セット図はステージ位置の検討や、この後に出てくるPAスタッフさんと本番までに機材の準備をするために必要だからです。
ちなみに、オファーをする際に、コラボレーションやアコースティック編成など、普段と違う特別な形のライブを提案することもあります。アーティストの負担にならない範囲で、企画や場所に合った新しい形態を提案していくのも、イベンターならではの関わり方だと思います。
例えば『タビノエ』では、minamoとmoskitooのコラボ演奏を依頼しました。両者の距離が近く、企画との相性も良いと思ったのですが、実際は初めてのコラボだったそうで、イベントを通してオリジナル楽曲がいくつも生まれるという嬉しい結果になりました。
運営スタッフを決める
イベントを一人で運営することは簡単ではありません。企画や規模に合わせて、必要なスタッフを洗い出し、早めにオファーを進めましょう。
特に音響スタッフ・PAは必須です。自分もアーティストの方に紹介いただきましたが、アーティストや会場に紹介いただくという方法もあります。お願いするときは「普段イベントでお願いしている音響スタッフさんがいればお知らせください」など伝えてみるとよいですよ。

また、企画者は当日いろいろな対応でバタバタするので、受付や誘導など、スタッフが何人かいると安心です。専門的な知識がなくとも手伝いやすい領域なので、身近で依頼しやすく、一緒にイベントを楽しんでくれる人に依頼しましょう。アルバイト代として謝礼金額はきちんと準備しましょう。
次の記事でも記載しますが、イベント情報の告知にあたり、フライヤーなどビジュアルをつくった方が効果的です。そのため、デザイナーさんも依頼が必要なスタッフになります。
そのほか企画に応じて、映像や照明演出やドリンク対応などスタッフが変わると思うので、都度スタッフを探し、お願いしましょう。
イベントの運営チームで現場へロケハンに行き、当日についてあれこれ話す時間は楽しいですし、そこからイベントをよりよくするアイディアが生まれることもあるでしょう。イベントを何度か同じチームで重ねると、以心伝心的に意図が伝わり、現場運営がよりスムーズになっていきます。

その他の記事について
次は、③音楽イベントの告知ビジュアル制作方法。フライヤーは第一印象を決めるについて紹介します。
その他の記事についても、以下のリンクから閲覧いただけます。
About

このブログ『音楽イベントの作り方』は、音楽イベント企画『orange plus music』が日々執筆しています。自分の好きな「穏やかな音楽」を好きになって欲しいという思いで、2018年よりプラネタリウム・ゲストハウス・演芸場・重要文化財など様々な場所でライブイベントを開催。また本業では会社員としてデジタルマーケティングやクリエイティブ制作の広告代理業にディレクターポジションで関わっています。音楽の場が継続していくために、自らイベントを企画する人が増えることを願って、企画段階から告知、準備、運営、事後まで含めた音楽イベントづくりの豆知識を記事で発信しています。