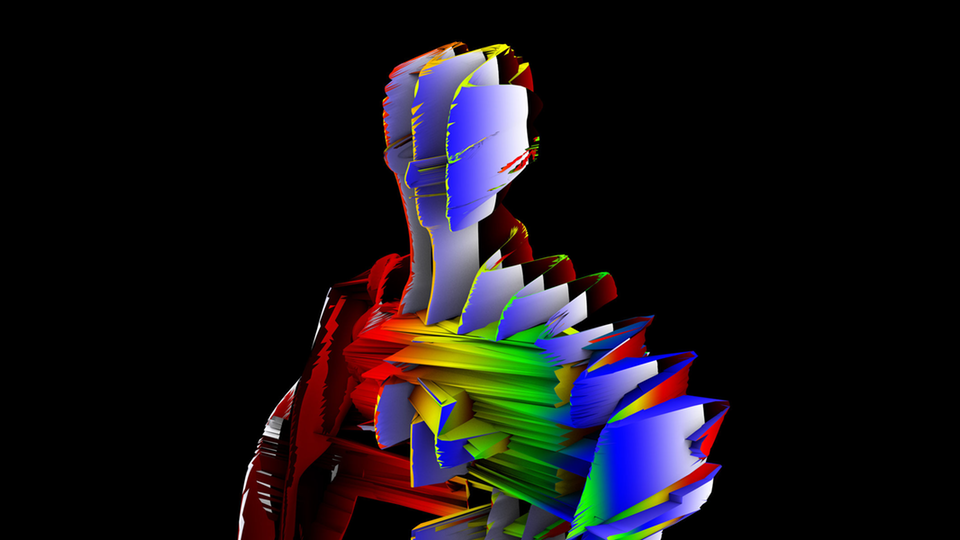「アンビエントな音楽」と聞いて、どんなイメージが浮かびますか?
去年はアジカンのゴッチさんが小説をアンビエントCD付きで出版されたり、ナカコーさんがアンビエントに特化したイベントを始められたりと、初めて「アンビエント」という言葉を知った人も多かったのではないでしょうか。
今年の抱負。とりあえず、アジカンの新しいアルバムを完成させる。ソロのアルバムの制作も始める。詩をたくさん書く。そして読む。朗読セッションもグイグイやる。アンビエント作品も作る。プロデュースも頼まれたらやる。それらを楽しく朗らかに。あと、きっついパーマをかけない。これ大事。
— Gotch (@gotch_akg) January 5, 2018
今回は改めて、アンビエントミュージック・環境音楽とは何か、どのような背景で生まれたのかを調べてみました。また、集中やリラックスにとどまらないアンビエントミュージックの魅力について書きました。
アンビエントミュージックとは、環境音楽とは何か
アンビエント(ambient)の意味は「周囲の」「環境の」であり、「アンビエントミュージック(ambient music)」を直訳すると「環境音楽」です。
“アンビエント”という単語は、「アンビエント広告」「アンビエント照明」という言葉や、「◯◯のアンビエント化」という表現で使われていたりします。これらには「周囲の環境に溶け込んだもの」というニュアンスがあることから、アンビエントミュージックは「周囲の環境に溶け込んだ音楽」と理解できます。
1988年に初めてアンビエントの概念をつくったとされるイギリスの作曲家ブライアン・イーノは、アンビエントミュージックを「興味深いけど無視できる音楽」という言葉で説明しています。
イーノが記した”As ignorable as it is interesting.”(興味深いが無視できる)という定義通り、集中的に聴く必要のない、聞き流しても構わない、だがしっかり聴こうと思えば聴くべきところのある音楽。
私たちの、アンビエント – 新・批評家育成サイト
アンビエントとして最初のアルバムと言われるイーノの『Ambient 1 Music for Airport』は、その名の通り空港のための環境音楽です。
彼の「ミュージック・フォー・エアポーツ」はケルン空港の環境に合わせて作られた。そのために、音がアナウンスに中断されても構わないこと、会話の周波数や速度から外れていること、空港のノイズと共存すること、そして飛行、浮遊、死といった空港の目的や雰囲気と結びつくことなどが考慮されている。
【論文】ブライアン・イーノの生成音楽論における二つの「環境」
Spotifyで聴けるのは、2004年のリマスター版。ゆっくり透き通る音が心地よいです。
アンビエントミュージックが生まれた背景
アンビエントミュージックはどのような背景で生まれたのでしょうか。歴史をたどってみると、西洋における芸術概念の変化が影響していました。
18世紀から19世紀の西洋では「作品」が音楽家の表現方法としてふさわしく、演奏の際に音楽を構成する音以外の音(自然音、機械音、人間の喋り声など)が入ることは好ましくありませんでした。そこで、コンサートホールという座って静かにじっと聴く施設がつくられていきました。
20世紀になり、そのような音楽鑑賞のあり方に異議を唱えたのがエリック・サティです。「家具の音楽」を発表しました。
それは家具のように目立たず、自己主張しない音楽、聴かれることを意図しない音楽であり、後のBGMを先取りするものであった。「芸術音楽」が作曲家の自我の表現をメッセージとして送り届けるべきものであるとするなら、これはそれと真っ向から対立するものである。この音楽は1920年パリの画廊で催された戯曲上演の幕間に演奏されたが、サティは座って聴こうとする聴衆に向かって、「おしゃべりを続けるんだ!歩き回って!音楽を聴くんじゃない」と訴えたと言われている。
CiNii 論文 – <研究ノート>「環境音楽」、または「環境」と「音楽」
サティの他にも芸術概念を変えていくような動きが続いていきますが、「何かをしながら音楽を聴く」という文化は、1920年代の技術発展でレコードとラジオが発明されたことによって更に加速していきました。
その後、第二次世界大戦後のアメリカで「音楽とは何か」を根底から問い直すような作品、ジョン・ケージによる無音の音楽「4分33秒」が生まれます。
無音の演奏であるため、聴衆はただ風の音や周囲の人の途方にくれたため息を聞くことになりますが、ケージはそこで聞こえるすべての音が音楽であるとして開くことを要求します。
ケージが求めているのは、与えられた音楽からあらかじめ作曲者や演奏者によってそこに封じ込められた音楽的意味を読み解く通常の音楽聴取ではなく、聴き手がその場で聴きとった音と戯れ、その戯れのなかから過去のさまざまな体験に応じて自分なりの音楽的意味を紡ぎだす、いわば「創造的聴取」である。それは主観や感情の表現・伝達としての音楽からの解放であり、既成の音楽と聴取のあり方を真っ向から否定し、制度化された耳を壊すことによって、新しい音楽聴取の道を開こうとする試みである。
CiNii 論文 – <研究ノート>「環境音楽」、または「環境」と「音楽」
YouTube越しに鑑賞すると、映像内の会場の音以外にも、自分の周囲の生活音や外の音、呼吸する音を意識するような不思議な体験になりますね。
こういった流れの後、20世紀後半にイーノが「アンビエント」という概念を打ち出していきます。きっかけのひとつには、とある病院での体験があったそうです。
1975年にイーノは交通事故に遭い入院し、ベッドで動けない状態にあった。お見舞いに来たジュディ・ナイロンが18世紀のハープ音楽のレコードを持って来て、彼女が帰った後、そのレコードをなんとかステレオにかけることができたが、ヴォリュームが小さすぎ、しかもステレオの片方のチャンネルから音が出ていない。しかし、ベッドに戻って横になってしまったので、それを直すことをせず、ほとんど聴こえない状態のままレコードをかけていた。その経験がイーノに新しい音楽の聴き方を示唆し、光の色や雨の音と同じように、音楽もまた環境の一部として機能するということに気づかせた。
Mikiki | ブライアン・イーノが『Reflection』で行う自己省察―自身の個人史遡るミュージック・フォー・シンキング・シリーズ最新作
最近では、ウォークマンやストリーミングサービスによってますます「何かしながら音楽を聴く」というのが当たり前になってきています。
また日本の忙しい労働環境を反映してか、アンビエントミュージックなど音楽に癒しを求める傾向が年々強くなってきていると個人的に感じています。
アンビエントミュージックを聴いて感じること
主観ではありますが、アンビエントと感じる音楽は、言葉が入らず、ビートは少なく、テンポは遅めで、メロディ展開が多くないものが多い傾向があります。
歌詞に心動かされたり、メロディでハイテンションになるような音楽とは違い、音のひとつひとつを味わって聴く楽しみがあります。
アンビエントミュージックを聴いている時は、大きく分けて以下のような気持ちになります。
- 集中できる
- リラックスする
- 自然の風景を想像する
- 環境を感じる
実際にTwitterで検索したつぶやき例がをいくつか掲載します。
集中できる(仕事、読書、考えごと・・)
アンビエントは声の無い音楽ですごく集中できるから作業用BGMにお勧めだゾ。
— Goose (@Goose_g3) 2017年5月1日
リラックスする(睡眠、入浴、落ち着く・・)
最近、アンビエントかけながら二度寝してる時がいちばん幸せ、それが趣味みたいな状態になってきた
— するり音 (@suruli) 2017年3月6日
外の雪を見つつ、暖色の間接照明に照らされアンビエントを聞いて飲むコーヒーの美味さ。
— さわや (@sawayan69) 2017年12月9日
自然の風景を想像する(雨、川、森、冬・・)
自然音いいですよね……深海の水中音や、宇宙の音と称した謎アンビエントが最近のお気に入り……
— かっぱすかはホニュ類 (@kappasukaorc500) 2017年7月14日
ぼちぼち2017年最高のアンビエントである「ゆく年くる年」が始まる
— gokki (@gokki) 2017年12月31日
環境を感じる(都市、喫茶店、モノレール・・)
雨。遠くで電車が通るアンビエントな音が聞こえてくる。近くで鳥たちがハイハットを鳴らす。何かにつけて人が歌おうとするがヴォーカルは無い方がいいようにも思える
— 風波旅人 (@kazenamitt) 2017年6月9日
ほか、アンビエントが大好きな人たち
今日は疲れたなー。
都会の路地裏で、車内で爆音で聴くアンビエントは最高やなー。ポテトが止まらない。— gorihead (@osoba5) 2017年12月27日
アンビエントラーメン(アンビエントを聴きながらラーメンを食べる行為)してる
— 無慾 (@_fuux) 2017年1月21日
自分も家でPC開いているときのBGMはだいたいアンビエントやエレクトロニカ系で、リラックスしながらも、作業に集中しているときが多いです。
実際、科学的にもアンビエント系の音楽で集中力が高まるという説もあったり、「1/fゆらぎ」というリズムが影響してリラックスできるという説もあったりします。
まとめ:アンビエントミュージックの魅力
「文化や芸術には、新しい世界の捉え方や知覚を広げていく力がある。」という言葉があります。
アンビエントに関する様々なことを調べながら、「なぜ自分はアンビエントミュージックを好きなのだろう?」と考えてたどり着いた答えも近いものでした。
アンビエントミュージックを聴くと、落ち着いた気持ちになります。作業や考えごとに集中できたり、リラックスした気持ちになったりします。
そういう良さに加えて、小さな音やちょっとした余韻に意識がいくことで、普段忙しくしているときには耳や目に入らないようなものに気付ける魅力があると感じています。

例えば、いつもは素通りしていた家の壁にたまたま陽が差していたのが目に入り、その模様を見て「綺麗だな」と思ったり。例えば、皿洗いをした後に、偶然閉め忘れた蛇口から落ちる水の音を「心地よいな」と思ったり。
そういう「日常にいつも存在しているものだけど、普段は気づかないかもしれないもの」だけど、「視点を当てると発見や驚きを感じるもの」に対して、より「見える」ようになる気がすること。これが、アンビエントミュージックを好きな理由です。
その場を支配する大音響ではなく、ふと聴きとられた控えめな音が今まで気づかなかった周囲の音環境に耳を開かせるきっかけを与えてくれる。〜(中略)〜それは「今まで気付かなかったものに気付いたり、感じ方が変わったり、日常的なものに新たな感性をもって接し、見たり聞いたりできるような音楽」と呼ぶことができる。
CiNii 論文 – <研究ノート>「環境音楽」、または「環境」と「音楽」
もちろんそれはロックバンドの歌詞に救われたり、(ART-SCHOOLの歌詞で生きていける気がしたり)、映画に感動したり(金曜ロードショーの魔女の宅急便、超よかった)と、アート作品に感動したり(”目”の作品に「気づかなくてもいいけど、気づいたらびっくり」という近い感覚を覚える)でも感じられることだと思います
でも、日常にある「興味深いけど無視できる」ものに気づけるようになるというのは、アンビエントミュージックのコンセプトにも合っているなぁと思うのです。
普段生活している中で物事を見る視点が増えると、余裕を持てたり、優しくなれる気がします。視点を増やしていくのは日々大事にしたいことだな、と自分は思います。
だから、もしこの記事をたまたま読んでアンビエントミュージックに興味が湧いた方は、ぜひ聴いてみてください。
おすすめアンビエントはこのブログの「アンビエント/環境音楽」タグがついた記事などからご覧ください。