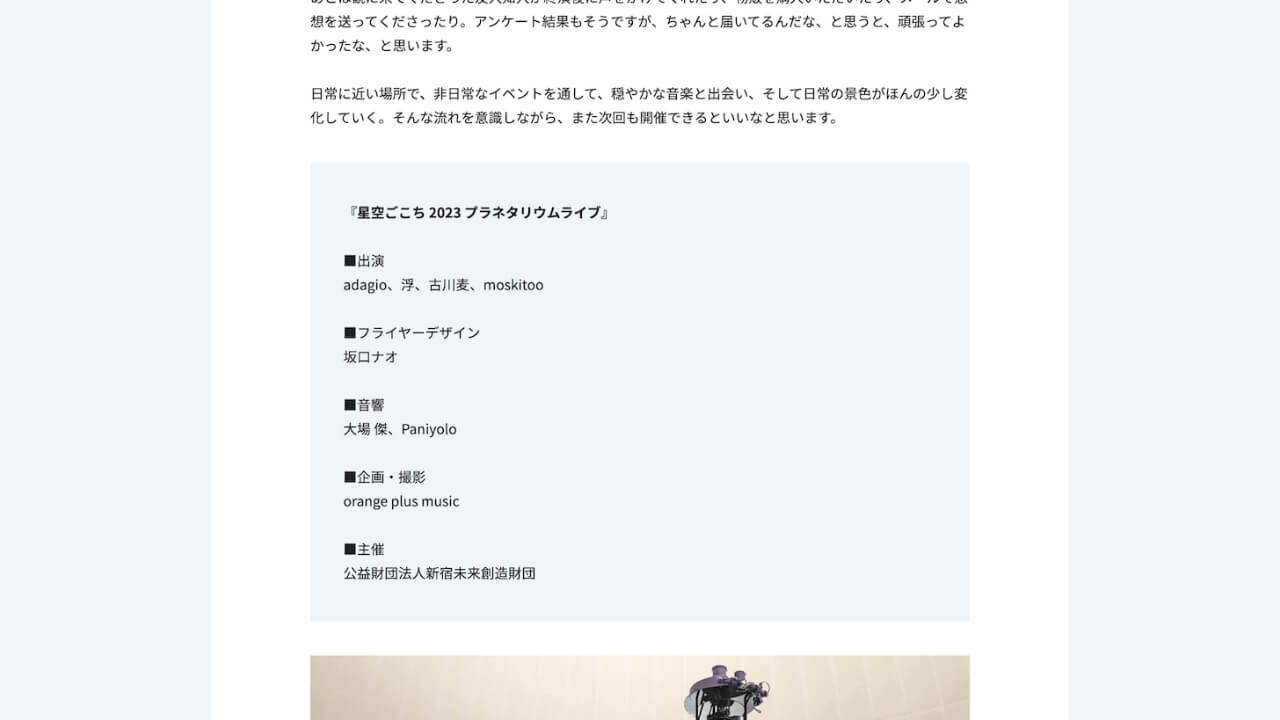企画した音楽イベントが終わった後に、ライブレポートを書くと様々なメリットがあります。
書いてすぐ役立つこともあれば、時間が経ってから効果を発揮することもあります。この記事では、ライブレポートを書くことで生まれるメリットや役立つ理由を3つ紹介します。
1. “後パブ”としての広報価値
イベントに来場した人へ向けて(短期)
実際に来場した人にとって、イベントレポートは当日の感動を思い出すきっかけとなります。
- セットリスト:聴いた曲を再度調べることができたり、ライブの曲順で聴き直すことができる
- 写真:来場者の場所から見えなかった雰囲気を知ることができる
- 出演者/参加者/企画者/スタッフの感想:イベントで他の方が感じたことを知ることができる
- その他、特別な情報:ライブ前後や楽屋裏の風景など、体験できなかった舞台裏情報を知ることができる
セットリストは、Spotifyなどのストリーミングサービスでプレイリストとして公開すると、聴きやすいのでおすすめです。
来場者には、参加時に決済サービスで取得したメールアドレスでお知らせをしたり、SNS(出演者のフォロワーなど)を通してイベントレポートを届けることができるでしょう。
当日の熱が冷めないうちにレポートを読むことで、イベントやアーティストへの更なるファンになってくださることが期待できます。
イベントに来場しなかった人へ向けて(短期)
イベント当日に来場していない人にとっても、イベントレポートは読みたいコンテンツとなります。
出演者のファンであれば、行けなかったライブをレポートを通して追体験できます。写真で会場の雰囲気を感じ、セットリストを聴き、感想から感動を想像することで、イベントを疑似体験できるのです。
ファンでなくても、レポートからイベントに興味を持ってくれることもあるでしょう。例えば、演芸場で開催したイベントレポートに対して「こういう企画って素敵ですね」というコメントと共にシェア頂いたこともあります。
こういう企画って素敵ですね。
音楽が生まれ出す空間。
それはかけがいのないものなのです。
→東郷清丸とMomが夜の街に「人の温かさ」を爪弾いた日 『Pluto Sparkle vol.2』ライブレポート – Gerbera Music Agency https://t.co/HI1ApK393D— Mitsu (@Mitsu24174273) November 30, 2022
長期的な広報価値
イベントが終わって数年後に、イベントレポートが読まれるということもあります。例えば筆者が企画しているプラネタリムライブは、検索経由で記事に辿り着くことが多いようです。
SNSでシェアされることもあれば、イベントの裏側が知りたいと問い合わせが来ることもあります。Web上にイベントレポートを残すことで、時間が経っても誰かに役立つ情報になる可能性があるのです。
2. 実績紹介としての資料価値
イベント企画の活動を続けていると、様々な場面で誰かに実績を伝えたい場面が出てきます。
- 新しい会場を借りる時
- 新しいアーティストにオファーする時
- 助成金や補助金の申請時
- 友人/知人に自分の活動を紹介する時
- 仕事の面接で経歴を説明する時
そんな時、イベントレポートがあると便利です。URLを1つ共有すれば、どんなイベントをやったのか、どういう雰囲気だったのかが分かります。
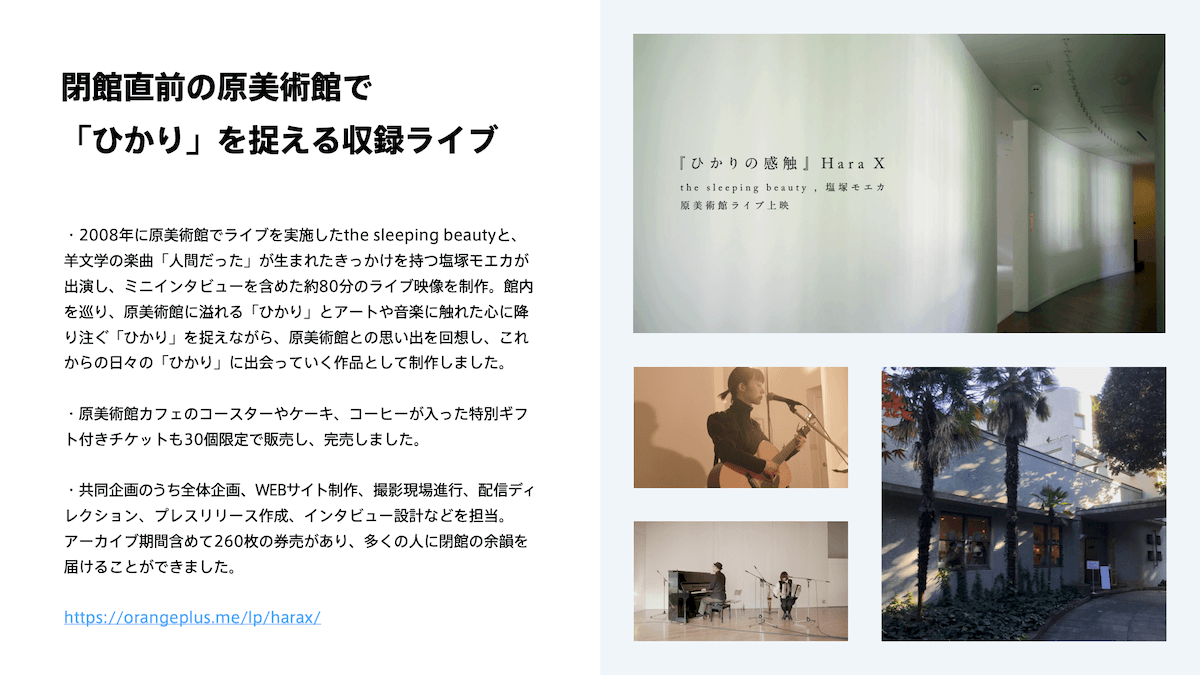
メイン資料を別につくり、補足資料としてイベントレポートを活用することもできます。資料にイベントレポートのURLを記載することで、必要な人に理解を深めてもらうことができます。
3. 関係者が思い出すための記録的価値
頑張って実現した企画イベント。企画者はもちろん、一緒にイベントを作り上げたスタッフや会場関係者、そして出演者にとっても、その日のライブはその日だけの特別なものです。
何かのきっかけでイベントのことを振り返る時に、レポートはとても役立ちます。写真、セットリスト、出演者/参加者/企画者/スタッフの感想などから、当日に見た景色や感じた気持ちを思い出すことができるでしょう。

それは次への活動への原動力になったり、インスピレーションとなったり、プラスに働くはずです。より詳細に思い出せるための記録的価値として、イベントレポートは役立つのです。
イベントレポートを書こう!
他にもイベントレポート関連の記事を書いています。少しでも参考なれば幸いです!
About

このブログ『音楽イベントの作り方』は、音楽イベント企画『orange plus music』が日々執筆しています。自分の好きな「穏やかな音楽」を好きになって欲しいという思いで、2018年よりプラネタリウム・ゲストハウス・演芸場・重要文化財など様々な場所でライブイベントを開催。また本業では会社員としてデジタルマーケティングやクリエイティブ制作の広告代理業にディレクターポジションで関わっています。音楽の場が継続していくために、自らイベントを企画する人が増えることを願って、企画段階から告知、準備、運営、事後まで含めた音楽イベントづくりの豆知識を記事で発信しています。